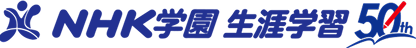書道講座(郵便講座)
美の規範である古典に学ぶ
古典を極める 漢字 楷書
学習期間
12か月
提出回数
10回
レベル
上級者
受講料
38,600 円
(税込/教材費・送料・指導料含む)

「古典を極める 漢字」コースのポイント
コース再編リニューアル
漢字の書の古典を一つ選んでじっくり臨書に取り組みたい方向けの講座です。
長い歴史のさまざまな審美感の中を生き残ってきた古典は書の美の規範です。 古典を臨書することで、いつの時代にも認められてきた字の美しさを学び、身につけるためのコースがこの「古典を極める・漢字」です。各コースからお手本(古典)を一つ選び、その古典をじっくりと臨書していきます。 臨書で培った技術は、他の古典臨書はもちろん、創作作品づくりにも大いに役立ちます。
ポイント01
1つの古典を1年間かけてじっくり学ぶ
学ぶ古典の個性や字形、線質の美しさなどじっくりと観察しながら取り組むことで、自ずと手本を見る力と、手本の用筆を再現する力が身につきます。それはそのまま書の技術力アップにつながります。 どのコースからでも構いません。ご自分の好きな古典が選べるコースからお入りください。 ※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。

ポイント03
実力確認と目標づくりに活用できる「書道検定」
NHK学園では年に4回、書道・ペン字検定を実施しています。ご自分の力量を客観的に把握し、普段の学習の成果を確認する場として、通信講座と並行して役立てることをお勧めします。書道講座の受講者にお届けする機関誌「書」に初回受験用の課題や申込書がついています。

「古典を極める・漢字」コース紹介
初回の受講時には以下のような課題に取り組みます







第1回 いろは歌 かな単体の学習
第2回 草かな 草かなの学習
第3回 第1回、第2回の復習
第4回 草かな 草かなの学習
第5回 第4回の復習
第6回 半切作品 歌一首の基本のおさめ方
第7回 第5回の復習を提出します。
第8回 半切の自由制作
第9回 第8回の復習を提出します。
こんな添削をお返しします
.jpg?width=576&height=755&name=1D1_201%20(1).jpg)

コースのお申込み
古典を極める 漢字 行書
学習期間
12か月
提出回数
10回
レベル
上級者
コース番号
1D121
受講料
38,600円
(税込/教材費・送料・指導料含む)
(税込/教材費・送料・指導料含む)
学習のてびき・リポート課題集1冊、添削ノート1冊、用紙セット(半紙、半切)、機関誌(期間中に2回別送)
※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。
---------------------------
楷書コース、行書コース、草書/隷書コースは、自動継続のコースとなりますの で、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。
お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際
(例:漢字「楷書コース」→漢字「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。
※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。
---------------------------
楷書コース、行書コース、草書/隷書コースは、自動継続のコースとなりますの で、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。
お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際
(例:漢字「楷書コース」→漢字「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。
コースのお申込み
古典を極める 漢字 楷書
学習期間
12か月
提出回数
10回
レベル
上級者
コース番号
1D120
受講料
38,600円
(税込/教材費・送料・指導料含む)
(税込/教材費・送料・指導料含む)
学習のてびき・リポート課題集1冊、添削ノート1冊、用紙セット(半紙、半切)、機関誌(期間中に2回別送)
※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。
---------------------------
楷書コース、行書コース、草書/隷書コースは、自動継続のコースとなりますの で、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。
お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際
(例:漢字「楷書コース」→漢字「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。
※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。
---------------------------
楷書コース、行書コース、草書/隷書コースは、自動継続のコースとなりますの で、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。
お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際
(例:漢字「楷書コース」→漢字「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。
コースのお申込み
古典を極める 漢字 草書・隷書
学習期間
12か月
提出回数
10回
レベル
上級者
コース番号
1D122
受講料
38,600円
(税込/教材費・送料・指導料含む)
(税込/教材費・送料・指導料含む)
学習のてびき・リポート課題集1冊、添削ノート1冊、用紙セット(半紙、半切)、機関誌(期間中に2回別送)
※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。
---------------------------
楷書コース、行書コース、草書/隷書コースは、自動継続のコースとなりますの で、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。
お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際
(例:漢字「楷書コース」→漢字「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。
※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。
---------------------------
楷書コース、行書コース、草書/隷書コースは、自動継続のコースとなりますの で、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。
お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際
(例:漢字「楷書コース」→漢字「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。
お問い合わせ
講座内容やお申し込みのご不安も、お気軽にご相談ください。
スタッフが丁寧にお答えします。